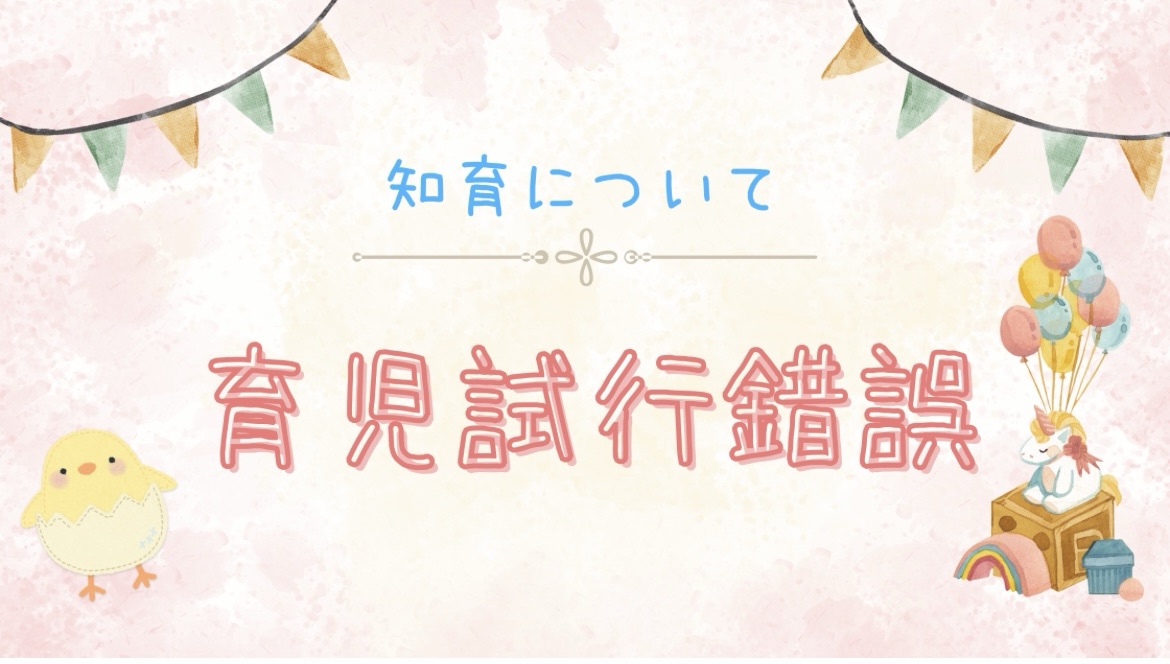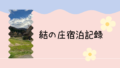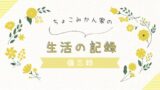子供が生まれてからゆるく始めた知育。
と言っても教室はお金がかかるし、結局我が家は家で親が頑張ることにしています。
現在子供は間も無く3歳。
これ意味あるのかなあと思いつつも続けてきたことが、言葉を発するようになって、もしかして意味があったかも?と親のやる気につながる成果が出てきました。
これまで続けてきたことを記載していきます。
日常生活の習慣化
インスタなどのSNSを見ると、イヤイヤ期の対策としても日常生活の習慣化がとても大事との情報が出て来ますよね。
特にイヤイヤ期などは、日常生活で毎日次に起こることがわかっていると子供のストレスも減ってイヤイヤが軽減されるとか。
とても良さそう!と1歳になった頃から、我が家もこちらを導入しました。
我が家が毎日行なっている大きな流れは以下です。
◯朝
起きて、お着替え、ご飯、保育園
◯帰宅後
そのままお風呂直行、ご飯、就寝。
この流れは子供が保育園に行き始めた1歳から約2年続けてます。
特に園生活では色々な菌を持ち帰ってくると聞き、家に帰ったら床を踏ませることなくそのまま風呂に抱き上げて連れていきます…
次の行動が分かれば子供もそのうち抵抗なくなると信じてこれまでやっては来ましたが…
2年ほど継続してる現在も未だに子供自身が嫌いな行動は嫌がります。笑
ちなみに我が子が嫌いなのはお風呂とお着替えです。ほぼ毎日している流れでさすがにわかっているはずなのに、高頻度で泣いて嫌がります。(むしろ次の流れがわかるからこそ抵抗が強い)
まあ嫌がっても次の流れが変わらないと学習しているのか、抵抗も比較的少なく、お風呂に連れていくと諦めてお風呂おもちゃで遊び始めたりしますが。
とはいえ、次の行動が決まっていると子供というより親の気持ちが楽になるので、個人的には取り入れてよかったなと思っています。
自分のことは自分で
こちらはモンテッソーリの本を読み漁った頃に、子供の自己肯定感を上げるためにも自分のことは自分でできる環境を整えてあげましょうという言葉に影響され、保育園に入園した1歳頃から始めてみました。
◯我が家が行ってきた取り組みは以下
・お着替えを自分で
・お風呂で体を自分で洗う
・お出かけの時の用意(保育園)を自分で
・ご飯を食べ終わったら自分で口を拭く
・食器の配膳
・歯磨きを自分で(仕上げ磨きは親)
※赤字のみが定着したものです。
やはり子供にも好き嫌いがあるんですね。
自分の意志が強く出始めてから習慣化づけようとすると難しいと聞き、まだあまりわかっていない頃からさせ始めてはいましたが、だめでした。
特にお着替えはどうやらかなり嫌いらしく…
子供に選択肢を与えると選んでくれることがあるとの情報を得て、どっちのお洋服にする?とか色々トライしてみましたが、ダメ。
食べ終わった後の口拭きもダメでした。
一度私がこの自分のことは自分で!にこだわり過ぎて
子供ができない時、かつ朝の時間がない時にやりなさい!と怒ってしまったことがありました。
泣きながら私の言う通り自分のことは自分でやっている我が子を見て、自分何してるんだろうと冷静になり大後悔しました。
自己肯定感を上げる為にする行動を無理やりさせることに何か意味があるのだろうか、まだ生まれて数年なのに…
それ以来、我が家では嫌がることは無理強いしない(ただし薬を飲んだりお風呂に入ったりと必要なことはどれだけ泣いててもしますが)ことを心がけてます。
やってと言われたら快くやってあげるようにしてます。
我が子は1歳から保育園に通っていることもあり、園ではどうやら自分でお支度なども頑張っているようなので…まあ家ではいいかなと。
とはいえ本人がやりたがることは可能な限りさせてあげるように、できそうにないことはできるように支援してあげるよう意識しています。
外遊び
家の中はもちろん、外で砂や葉っぱなど自然に触れることが一番良い刺激になると聞き、夏の暑い時期と冬の寒い時期(冬は着込めばいけますが、親がつらいので…)以外は、やる気を出して公園に連れて行っています。
平日は毎日保育園なのですが、外に出られる気候の時期は迎えに行った後そのまま公園に連れていき、子供が帰りたがるまでなんとなく遊んでます(秋は日が落ちるのが早いので公園に着く頃にはすでに薄暗く、真っ暗闇の中で遊んでることも。笑)
これは知育効果はまだわかりませんが、走ったりボール遊びなど、体を動かすことが好きなようで、このまま好きなままいてくれたらいいかなあと思っています。
(私が運動音痴なので…)
机の導入
自分の机があると集中しやすくなると聞き、1歳半頃机を購入しました。
最初の頃は机で何かしたりはあまりせず。
それでも自分の机があることは嬉しかったようで、よく座ったりはしてました。
2歳になった頃あたりから、お絵描きや粘土など少しずつできることが増えてきたので、そういうことは机でやるんだよと伝えるようにしてきたら、ちゃんと机に座って作業するようになってきました。
とはいえ集中力がついているかと言われると、そこは少し疑問なところ。
集中していそうな時は声をかけず後ろで待機するだけにしてはいますが、
高頻度で、できた、みて?みて?と子供から私のことを振り返って声かけてきます。
ただ、親としてかなり助かるのが、家が汚れそうな粘土やペンのお絵描きなども、机でやろうねとずっと声掛けしてるからか、机を離れてペンやシールを持ちながら家の中を走り回るようなことはあまりないです。
一応我が家まだ新築なので、子供がいると家は汚れ傷がついていくものだとわかりつつも、これはかなり安心なところでした。笑
絵本
できれば本好きにさせたい、語彙は本から増える、◯歳までに◯冊!など育児書などを見ると書いてあり、我が家も目が見え始めたかな?というレベルの状態あたりから意識して絵本は読んでいます。
ただ育休中はともかく職場復帰後、子供が保育園へ通うようになってから、我が家の絵本習慣は迷走。
絵本を生活の中に取り入れられず、週の大半は読まず、思い出した頃に読む、という日々を過ごしていました。
子供から読んでと言われたら読む…くらい。
とはいえ我が家がずっと続けていることが一つだけありました。
毎月図書館で本を借りること
です。
図書館は本当にありがたいですね。
人気の絵本はたいてい揃っているし、次に予約している人がいなければ貸出の延長も可能。
我が家は図書館を利用して、
今月の絵本を決め借りてくる!
これだけはなんとか守ってました。
(やる気のない時期はほぼ読まず返却もありましたが)
おかげで本を新しくした月初は子供の本への食いつきもあり、読んでーと言ってくることは多かったです。
とはいえ、やはり毎日読む習慣は作りたい、せめて一冊だけでも…ということで我が家も試行錯誤してきました。
試行錯誤してきた時間帯は以下
①朝起きた時
朝起きて、ご飯を食べる前に絵本を読む
これは数日やってみましたが続かず。
お休みの日はともかく、平日の朝そんなことしている余裕がなかったからです…
可能ならギリギリまで寝かしてあげたい、起こしたら急いで準備して保育園に、の生活なので、そこに絵本をゆったり読む時間は皆無でした。
②夜寝る前
恐らくこの時間帯が多くの親御さんが取り入れている習慣かなと思います。
ただ、これも我が家は続かず…
①と同様、平日の夜は仕事が終わって保育園に迎えにいき、お風呂、ご飯、もう寝る時間!のバタバタ。
寝る前に多少時間があるも、子供がパズルやったりとか、お絵描きしたりとか、親として取り組んで欲しい遊びをしていたりすると、その時間を減らして、絵本読もう!とはなかなか出来なかったんですね。
また、我が家は寝る直前にドリームスイッチを見るようにしているので、絵本を読んで、その後ドリームスイッチ、の流れが上手く作れずでした。
③ご飯の後
結局我が家で定着した絵本の時間はここになりました。
賛否両論あるかと思いますが、我が家はご飯の後椅子に座り、デザートの果物を食べている間に読むことにしました。
お米やおかずなどのちゃんとしたご飯の時はさすがにテレビ、絵本や遊びはなしとしてますが、この時くらいはいいかなと…
この時間で定着させて良かった点
・親が好きな絵本を選べる。
毎月図書館で今月の絵本を借りてきますが、子供が遊んでる時にこれ読むよーと持っていくと、それやだ、これがいい などと子供の主張に合わせて毎回同じ絵本になっていました。
それはそれでとても良いですし、同じ絵本を何度も読むのも大切だと思いますが、これも読んでほしいなという親の希望の絵本もあるかなと。
果物を食べながらとかだとなんとなく機嫌良く聞いてくれます。
・親の負担が減る(私だけ?)
生まれたばかりの頃の絵本は、1ページに一文字など、一冊を読んでも一瞬、もう一度読んでも負担がなかったのですが、大きくなってくると推薦図書の文量も増え、一度読んだらもう二回目はきつい…
特に寝る前に子供と自分の時間を長時間拘束がどうしても出来なかった…
私は本が嫌いなわけではなく、比較的好きではあるのですが、毎日どこかに組み込むとなるとなんだか義務、無理やり感があって、嫌いになってしまいそうでした。
果物をゆっくり食べてる間ならまあそんな時間のロスもないし、ということで親の気持ちが楽になりました。
ものを食べながらで集中してないかなと思いきや、結構この時間に読んでる絵本の内容を覚えているみたいで、会話の時にふと、絵本の内容を話してきてくれたりします。
もちろん他の時間に子供がこれ読んでと持ってきてくれる時は、気が済むまで同じ本を繰り返し読んであげるようにしてます。
子供への対応で意識していること
・毎日愛情を伝える
小さい頃から毎日のように、それこそ息をするように大好き、かわいい、と伝え朝起きた時と寝る時はちゅーを習慣化しています…
(この時以外も子供のほっぺには常に顔をくっつけてるくらいですが…)
おかげで言葉がしっかり出ている3歳時点で、
結構な頻度で
まま、すきだよと伝えてくれます。デレデレ。
(え、クールになっていくのはここから?)
・親の感情や都合で怒らない
なかなか難しいですが、親の感情や子供に関係のない理由ではなるべく怒らないよう気をつけています。
とはいえ、余裕がないとちょっとしたことで理不尽に怒ってしまうこともあるので、なるべく心や時間に余裕を持って日々過ごせるよう意識しています…
(それでも余裕なくイライラしてる時は、その後ごめんねと謝って許してもらいます…)
・ダメなことは理由を伝える
0歳のまだ言葉がわかっていないと思われる頃から、ダメなことは理由を伝えた上でしちゃいけないと伝えるようにしてきました。
例えば、我が家では駐車場など車が来る所では必ず手を繋ぐようにしていますが、子供って手を離して駐車場の中を走りたがったりしますよね。
車が来たら危ないから、ここでは手を繋がないといけないよ。怪我したらまま悲しいよ。
と理由を根気よく伝えてきたことで、最近は自らここ危ないねと手を繋いでくれるようになりました。
他にも公園で危ないことをした時、
電車や公共の場で大声を出して走ろうとした時、他の家の花を摘もうとした時など、何かあるたびに根気よくダメな理由を伝えて来たら、言葉がわかるようになってきた現在、納得のいく理由の時はちゃんとその行動をやめるようになってくれました。
(公園でもっと遊びたいなど自分の主張が強い時はだめですが…)
・親の主張を変えない
公園から帰る時
お風呂に入りたがらない時(休日家に一日いる日)
子供がまだ遊んでいるけどそろそろ寝る時間な時
など、親と子供の戦いは毎日ありますよね。
例えば公園で遊んでいる時も、そろそろ帰るよと伝え、もう一回ブランコ、あと一回滑り台、などどんどん延びていくことも…
なので、まず子供に今の遊びをあとどのくらいしたら次の行動にうつれるかを確認、相談の上一緒に決めます。
例えば公園にいるなら、
そろそろ寒いから帰ろうと思うんだけど、どうかな?まだ遊びたい?じゃあ今乗ってるブランコ終わったら帰るで良いかな?
子供がそのルールを承諾してくれたら、その後どれだけ泣いても無理やり連れて帰ります。
これを導入したばかりの頃は、かなりの抵抗がありましたが、約1年、このルールを徹底してきたことで、多少泣いたり嫌がっても、比較的すぐ納得してくれるようになりました。
テレビについて
我が家はテレビを基本見せないようにしています。
元々私がテレビを見る習慣があまりなく、子供が生まれる前から、テレビを見ずに生活していたので苦ではありませんでした。
0歳の頃から、教育番組やアンパンマンなど子供が好きそうなものは何も見せていません…
ただ、唯一テレビを起動させるのはDWEのDVDを見せる時のみ。
なぜテレビを見せていないかというと、テレビを見てる時間に他の知育をしたい、絵本を読んでほしいというのはもちろんですが、1番の理由はDWEのDVDに可能な限り長くはまってほしいから…
DWEの教材、個人的には気に入ってますし、質の高いものだとはわかっているのですが、
あまりおもしろくない…
映像も古く動きも少ないので、もし現代のテレビアニメの面白さを知ったら多分もう見てくれないなと思います。
(ただ私としてはそこが気に入ってます。刺激や動きが少ないので、絵本感覚で見せられるし、テレビ見せてる!という感じがしません)
なので、うちのテレビはミッキーを見る目的でしか起動させてません。
子供も物心ついた時からそうなので、特に疑問にも思わず、DWEのDVDを満足してみてくれています。
とはいえ、病院や実家、友達の家に行った時はおもしろそうな子供向け番組がテレビにうつっているので、いつまでこの状態に満足してくれているかは分かりませんが…
好きなものを食べる時間を決める
我が家は夜ご飯の後にデザートの時間があります。
また週末だけですが、15時過ぎにおやつの時間を設けています。
我が子は食い意地がかなりはっており、常にご飯のことばかり考えているようで、
お弁当を作って外にお出かけをしようものなら、行きの車中ではおにぎり食べようか、
目的地に着いたら、おなかすいた、たべようか
と、口を開けば食べ物のことばかり…
特にお菓子や果物は底なしに食べたがるので、食べたがったら、果物は夜ね!お菓子はおやつの時間にね!と伝えることを心がけて来ました。
最初のうちはものすごく抵抗、外でも地面に転がって泣いて叫ぶこともありましたが、段々とその時間になれば食べれることがわかってきたのか、多少嫌がりますがそれまで待ってくれるようになりました。
ただ、親がそれを忘れないこと、万一お出かけの都合などでその時間を設けられなかったら後日フォローすることは気をつけるポイントでした。
フラッシュカード
フラッシュカードも賛否両論ありますが、我が家はこちらを0歳時の頃から導入しています。
「0歳時の頃から」キリッ(`・ω・´)
と言いましたが、0歳時の頃はダイソーにて購入した小さなカードをなんとなく思い出した時にフラッシュする程度でした。
1歳になった頃は、少しだけやる気を出して、
フラッシュカード無料教材をネットでさがし、雲や数などをA5サイズに印刷して、こちらも気が向いた時にフラッシュしてました。
(ダイソーのカードは小さすぎてフラッシュしにくかったというのもあります)
2歳直前、ついに更にやる気を出して七田式さんのドッツカードを購入。毎日夜やり始めました。
ただ、毎日フラッシュする内容が決められており、説明本をみながら毎晩セットするのが億劫になり、少しずつ疎遠になっていきました。
やる気がまた復活したのは2歳半の頃、
ついに七田式さんの有名教材かなえちゃんに手を出しました。
こちらなかなかのお値段もするので、正直買った後不安と後悔、しかも大量。こんなにできるの?と心配でしたが、なかなかの金額を投資してしまったので、これもどこかに日常的に取り入れなくては!と決意。
そして取り入れたのは…
絵本と同じ夕食後デザートの時。
この時間に、かなえちゃんと国旗カード、ドッツカード、国旗カード(国旗カードのみ手作り…)をフラッシュし始めました。
フラッシュカード、意味あるのかなあ、記憶力があがる、すぐに覚えられると聞くけれど、我が家はなかなか成果は出ませんでした。
たまに途中でフラッシュを止めて、これ何?と聞いても、???の顔。
意味ないのかなあと諦めつつもなんとなく毎晩やってました。
3歳直前のとある日、子供と初めて訪れる公園で遊んでいました。そこには風車があり、珍しいなあと思っていたのですが、その日の夜いつも通りフラッシュしてたら、
まま、今日見た風車があるねと子供が途中で話しかけてきました。
確かに私はその日風車の絵が混ざっているカードをフラッシュしていました。
風車、ちゃんとインプットされてたんだーと感動したのを覚えています。
その頃から、少しずつ、フラッシュした内容、覚えてるかも、と感じるようになりました。
途中で止めて、これは?と聞くと、今まで親子の会話では出てこなかった単語なのにちゃんと答えてくれたり、カードを私が読み上げる前に次の順番のカードを子供が先に読み上げたりし始めました。
どのくらい続くか分かりませんが、子供が嫌がるまではフラッシュカード続けて行こうと思っています。
これらが現在までゆるゆると我が家で続いている知育の取り組みになります。
知育を本気でやっている人にとっては当たり前の内容、今更…と思われることかもしれません。(すみません…)
我が子はまだ3歳児なので、成果が目立って出ているものではないですが、この先大きくなった時少しでも力になっていると良いなあと思いつつ、続けていこうと思っています。